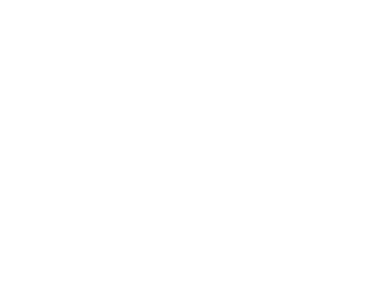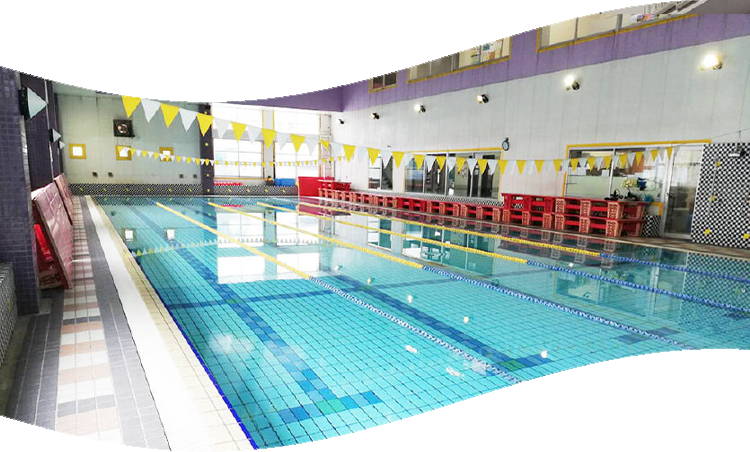目次
はじめに
多くの親御さんが「どんなお子さんに育って欲しいか?」と言う質問で以下の回答をしています。
「自分らしさ(個性)のある子」
ケーニーズコラム
https://kanyes-club.com/column/主体性
1.「外的動機付け」と「内的動機付け」
お子さんの「ヤル気」には、大きく分けて2つの種類があります。それが「外的動機付け」と「内的動機付け」です。
外的動機付けは、「ご褒美がもらえる」「怒られたくない」「褒められたい」といった外側から与えられる理由によって行動するヤル気です。たとえば、「宿題をやればゲームができる」「ママに怒られたくないから習い事に行く」といった形がそれにあたります。
一方で内的動機付けは、「自分でやってみたい」「面白そう」「もっとできるようになりたい」といった内側から自然に湧いてくるヤル気です。誰かに言われたからではなく、自分の気持ちで行動する点が特徴です。
この内的動機が育っているお子さんは、自分から動く力「主体性」があり、「自律」的に行動する習慣が身についていきます。また、「できた!」という達成感が「自己肯定感」を高め、失敗を恐れず前に進む「挑戦力」が育まれていきます。
2.「外的動機付け」の特徴
お子さんの未来のためには、「外的動機付け」に頼りすぎない工夫が必要です。
3.「内的動機付け」の特徴
内的動機付けによって行動するお子さんは、「やってみたい」「もっと知りたい」と、自分の気持ちを原動力に行動します。たとえば、絵を描くのが好きな子が「もっと上手に描きたい」と、自分から練習を重ねていく──そんな姿がその典型です。
4.「内的動機付け」を育てるために
「どうやったら、うちの子にも『ヤル気スイッチ』が入るんだろう?」
と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。その『スイッチ』は、実はちょっとした関わり方によって、育てることができます。
まず大切なのは、子ども自身に「選ばせる」ことです。たとえば、「宿題、先にやる?それともごはんのあとにする?」というふうに、選択の自由を与えることで、自分で決めたという実感が生まれます。これは主体性や自律性の一歩になります。
次に意識したいのは、結果よりも“過程”を褒めることです。「100点で偉いね」よりも、「最後まで自分で頑張ってたね」「難しかったのに、工夫して解いたね」と声をかけることで、「頑張った自分がすごいんだ」と子どもは感じます。こうした声かけは、自己肯定感を育てるうえでとても効果的です。
また、失敗したときには、まず、チャレンジしたことを褒めてあげましょう。そして、すぐに正解を教えるのではなく、「どうしたらうまくいくと思う?」と問いかけてみるのもおすすめです。自分で考えて試すプロセスを大切にすることで、【内的動機付け】を育むとともに『考える力』も伸びていきます。
こうした日々のやり取りを通して、お子さんは「やってみたい」という気持ちを大切にできるようになります。親御さんも忙しいと思いますし、すぐには効果が現れないかもしれませんが、お試しされることをおすすめします。
5.失敗こそチャンス
お子さんが何かに失敗したとき、その瞬間こそ「内的動機付け」を育てる最大のチャンスです。京都大学の研究でも、失敗した時にドーパミン神経細胞が活発化してドーパミンが分泌され、挫折を乗り越える意欲につながることがわかっています。「もう無理」「やりたくない」と落ち込むときこそ、関わり方がカギになります。
たとえば、逆上がりの練習で何度やってもうまくいかず、悔しくて泣いてしまったとき。「失敗しても、頑張ってる姿すごくかっこよかったよ」「チャレンジしたこと自体がすごいことだよ」と伝えると、お子さんの心には「やってみてよかった」という思いが残ります。
このように、失敗の体験を「否定」ではなく「挑戦の証」として肯定的に受け止めてもらえることで、お子さんは「もう一度やってみようかな」と思えるようになります。これは、「自律性」や「自己肯定感」の両方を高めるために大切な土台です。
「どうしたら次はうまくいくと思う?」という問いかけも効果的です。失敗を通して自分で考える機会が与えられることで、次への内発的な意欲が湧いてくるのです。「どうしたら」の後には解決策を考える言葉が続きます。「どうしたら」は課題解決力を高めるために重要な「魔法の言葉」です。
失敗を責めるのではなく、「成長のチャンス」として一緒に受け止める姿勢が、お子さんの「自分でやってみたい」という気持ちを後押しします。
小学生期、特に中高学年は「ゴールデンエイジ」とも呼ばれ、心と体、そして思考力の発達が大きく進む時期です。この時期に「やりたい」という気持ちを大切にし、自ら動く経験を積むことが、将来の自律性や主体性につながっていきます。
内的動機付けが育ちやすいこの時期に、「やらされる」体験ばかりになってしまうと、「自分でやる意味」を見出す力が弱くなってしまいます。逆に、「自分で考えてやってみた」「うまくいった」「できなかったけど楽しかった」などの体験が積み重なると、お子さんは自分の選択に自信を持てるようになります。
内的動機付けは家庭だけで育つものではありません。学校の先生や習い事のコーチなど、お子さんに関わるすべての大人の声かけや関わりが、大きな影響を与えます。
ケーニーズクラブでもこの「内的動機付け」に繋がる働きかけをしています。
例えば、ジュニアスイミングの進級テストでは、合格できなかった全てのお子さんに「結果シート」を配布しています。そこには次の課題を見える化しています。合格・不合格だけではなく、お子さんとコーチ、そしてご家庭でも「〇〇ができたら合格だね」と前向きな会話をしていただけるようにお伝えしています。
また、学童保育ではお子さんが「ありのままに好きな時間を過ごす」見守り保育をしています。何をするか、いつするかはお子さん自身が決めて過ごします。お子さん自身は無意識に「自分で考え、選び、行動する」を繰り返しています。
<関連サイト>
ケーニーズ ジュニアスイミング
https://kanyes-club.com/junior
ケーニーズ 学童保育
https://kanyes-club.com/gakudou
まとめ
今日からできる5つのヒントを、もう一度振り返りましょう。
◎「やってみたい?」とお子さんに選ばせる関わりを意識する
◎結果ではなく過程を認め、失敗も成長の一歩として受け止める
◎お子さんの気持ちに寄り添う声かけをする
◎家族以外の大人とも連携して“やる気”を応援する
◎家庭でできる小さな習慣をコツコツ続けていく
お子さんの「内的動機付け」を育てることは、自律・主体性・自己肯定感の土台をつくることです。将来、自分らしく生きる力にも直結します。ケーニーズクラブの企業理念「個性を活かして、自分らしく輝くお子様の育成」を叶えるためにも、すべてのスタッフがお子さんへの言葉がけや対応、システム等でお子さんの内的動機付けが育まれるよう努めています。
お子さんの「やってみたい!」は、ママやパパの温かいまなざしから始まります。一緒に、未来へ羽ばたく力を育てていきましょう。